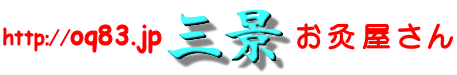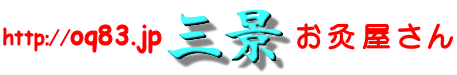|
2025年11月 No 95
|
閉じる
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 身体と精神 Part1 |
ナイジェル・ドーズ |
| 不安症について思うこと |
山岡傳一郎・石田 亮子 |
| 精神神経症、灸療法と深谷伊三郎 |
フェリップ・カウデット |
| 不安症に対する鍼灸 |
ピーター・エックマン |
| 不安の治療 |
水谷潤治 |
| 不安症の臨床 |
猪飼祥夫 |
| 不安との闘い |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 不安の臭い |
高橋英生 |
| あきらめて気楽に生きる |
岩下秀明 |
| 真の不安 |
トーマス・ソーレンセン |
積聚治療入門 Part31
不安に対する積聚治療 |
高橋大希 |
不定愁訴と不安を抱える症例について
Part1 |
形井 秀一 |
| ストレス性の便秘の鍼灸治療 |
髙橋 正子 |
| 子どもの治療は母子同治 |
小松 広明 |
| 術後疼痛の治療 |
ジョン・ヤールスフェルド |
鍼治療とオステオパシー手技による
腰椎穿刺後頭痛の予防 |
マーク・ペトルッツィ |
玉井天碧の「指圧法」
指圧のルーツを探る Part 16 |
スティーブン・ブラウン |
| 積聚療法 英国初のワークショップ |
デイビッド・スハルト |
IAALM による
「言霊いのち生命医学」講座 |
スコット・バーテル |
|
2025年07月 No 94
|
詳細
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 難しい質問 |
ボブ・クイン |
| 何を刺激するのか? |
前田 篤希 |
| 東洋医学における刺激について |
ピーター・エクマン |
画一的な方法を超えて
灸と適切な刺激の再考 |
オラン・キヴィティ |
| お灸のドーゼの決定にTRPは役立ちますか? |
マーリン・ヤング |
| 現代に通用する灸療法 |
水谷 潤治 |
| 治療を終える潮時 |
高橋 英生 |
| 生命力と治癒力を高めるために |
岩下 秀明 |
| 深谷灸法における適切な刺激量 |
フェリップ・コウデット |
| ちょうどいい刺激の反射回路を作ろう |
校條 由紀 |
| 変化こそはすべて |
トーマス・ソレンセン |
| 足りないくらいの刺激量を基本に |
香取 俊光 |
積聚治療入門 Part 30
適切な刺激量 |
高橋 大希 |
| ちょうどいい刺激-非接触鍼 2 |
西山 昭弘 |
| 鍼灸における適切な刺激 |
バート・ウォルトン |
| 石坂流鍼術における刺激の考察 |
久保田 直紀 |
| シリーズ操体 part 4 |
小松 広明 |
| 指の関節痛の灸治療 |
猪飼 祥夫 |
| 刺激は患者の反応によって |
ジョン・ヤースフェルト |
| 冷え性に対する灸治療 |
髙橋 正子 |
| ECIWO脊髄点 |
ファルク・サヒン |
| NAJOM経絡、経穴アンケートに寄せて |
松田 博公 |
セミナーレビュー
チャーリー・ニューベリーと古里式を探る |
ルネ・ミンク |
| TSTセミナーバンクーバー2025 |
ダニエル・シルバー、サラ・バーグマン |
| 大上勝行 伝統医学講座ロサンゼルス |
大上 遥 |
レポート
第8回日本鍼灸海外研修ツアー 京都2025 |
前田
篤希 |
|
2025年03月 No 93
|
詳細
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 2024年NAJOM会員アンケートから見えるもの |
ボブ・クイン |
NAJOMアンケートへの回答
視覚障害者と象のように |
ジェフリー・ダン |
| 灸治療とその効果について |
水谷 潤治 |
NAJOM新たな事実
一律では全てに対応し難い |
ジェフリー・ダン |
| 相火とは何なのか? |
ピーター・エックマン |
新しい発見とその事実
非接触鍼 |
西山 昭弘 |
| 操体プレシャー Part2 |
岩岡 博 |
新たな3 つの発見
海外向けの操体技術を深掘り |
小松 広明 |
| 胸の目から世界を見る |
ローレン・ヘイス |
二つの啓示
私の臨床に革命をもたらした症例 |
ゼヴ・ローゼンバーグ |
| 急性症状にやさしく対処するスパイラル治療 |
マーク・ペトルッツィ |
| 安田無観先生から学ぶ送りこみ刺法の真髄 |
ヘザー・マヤ・スズキ |
| AHA!(なるほど!)の瞬間をつなげる |
パメラ・ファーガソン |
積聚治療入門 Part 29
アッと気づいて学んだこと |
高橋 大希 |
| 刺絡と火鍼による浮腫の治療 |
本多 進 |
鍼灸教育における救急対応
日本の事情 |
谷田 保啓 |
| めまい(眩暈)の鍼灸治療 |
髙橋 正子 |
鍼灸の自然治癒力
心臓弁膜症、がん、リカバリー服 |
校條 由紀 |
| 追悼 |
ジェーン・ウェン |
| 生命の鼓動 Part 2 |
アンソニー・トッド |
| 運動器疾患の診察・診断・治療(北辰会方式)Part 2 |
藤本 新風 |
鍼および機能性医学での
潰瘍性大腸炎の処置 |
ファルク・サヒン |
玉井天碧の「指圧法」
指圧のルーツを探るPart 14 |
スティーブン・ブラウン |
| 松本岐子に追いつく |
カット・アオ |
コトタマ・イノチ・メディスンの紹介
サンタフェ |
スコット・バーテル |
|
2024年11月 No 92
|
詳細
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 日本鍼灸のオデッセイ |
ピーター・エクマン |
| お灸を理解する新しいモデル |
マーリン・ヤング、オラン・キヴィティ |
| 痛みは気の乱れの表現 |
トーマス・ソレンセン |
首藤流 臨床記
帯状疱疹後神経痛 |
村田 守弘 |
運動器疾患の診察・診断・治療
(北辰会方式) |
藤本 新風 |
| 痛みに対する深谷灸のコツ |
フェリップ・カウデット |
| 操体の流儀:受け継がれる触診と操法 |
小松 広明 |
| 操体プレシャー Part 1 |
岩岡博 |
| 透熱灸における繊細さと特異性 |
マーク・ペトルッツィ |
高橋英生
打鍼をニューヨークへ |
トム・インゲグノ |
温竹療法による痛みの緩和
身体反応システムへの熱の適用 |
オラン・キビティ |
低周波鍼通電療法から
鍉鍼によるナソ治療・ムノ治療へ |
岩下 秀明 |
| 末期ガンの疼痛寛解法 |
猪飼 祥夫 |
| 足元に禅を見いだせないなら、どこを見る? |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 五十肩に対する鍼灸治療 |
校條 由紀 |
| 梅核気(ヒステリック球)の鍼灸治療 |
髙橋 正子 |
| 頸部筋痙攣の痛みを即座に和らげる |
ラーマン・カプア |
積聚治療入門 Part28
痛みと積聚治療 |
高橋 大希 |
| 生命の鼓動 |
アンソニー・トッド |
| 経絡とツボについての進化論パート2 |
マーリン・ヤング |
玉井天碧の指圧法
指圧のルーツを探るPart 13 |
スティーブン・ブラウン |
私の考える経絡試論
藤木俊朗の世界(経絡論)をベースに-Part 3 |
戸ヶ崎 正男 |
| 大上勝行先生セミナー |
大上 慎吾 |
| 第7回日本鍼灸海外研修ツアー in 京都 |
前田 篤希 |
岩岡博
操体指圧・正体針法ワークショップ |
ジェーン・ウェン |
|
2024年07月 No 91
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 経穴の位置は邪気でわかる |
高橋 英生 |
| 経穴についての考察 |
ボブ・クイン |
| 経絡とツボとは何か |
バート・ウォルトン |
| ツボは虚の表現 |
トーマス・ソレンセン |
| 首藤流鍼灸術で常用するツボ |
村田 守弘 |
| 経絡と経穴 第1章 |
マーリン・ヤング |
| 経筋研究から明らかになったツボと経絡の関連 |
篠原 昭二 |
| 特效穴 |
水谷 潤治 |
| 臓腑経絡の理論と実践 |
藤本 新風 |
| 石坂流鍼治十二條提要に観る治療穴 |
久保田 直紀 |
| ツボを冷やす、温める |
猪飼 祥夫 |
| ツボとは何か |
香取 俊光 |
| 経絡について―臨床の立場から―Part 2 |
形井 秀一 |
| 息を分ける−治療の紐を解きほどく経穴と経絡パート2 |
アンソニー・トッド |
私の考える経絡試論
藤木俊朗の世界(経絡論)をベースに Part 2 |
戸ヶ崎 正男 |
| 積聚治療入門Part27 経穴と積聚治療 |
高橋 大希 |
| ボディワークの観点から考えるツボ |
パメラ・エレン・ファーガソン |
シリーズ操体
橋本敬三の臨床を再現するためのロードマップ Part3 |
小松 広明 |
| 船水隆広流鍉鍼による気・血・津液の症例 |
マーク・ペトルッツィ |
| 自己免疫疾患の処置における脾臓点 |
ファルク・サヒン |
| 中医薬による貨幣状湿疹の治療 |
ケリー・ウェストハウザー |
| 乳腺炎の鍼灸治療 |
髙橋 正子 |
| 玉井天碧の「指圧法」 Part 12 |
スティーブン・ブラウン |
| 船水隆宏式 鍉鍼テクニック(TST) |
エリック・マイケルセン |
書評
ピーター・デッドマン著「気功:身体、呼吸、心の養成」 |
ボブ・クイン |
|
2024年03月 No 90
|
詳細
|
在本 |
| アンサングヒーロー |
水谷 潤治 |
| NAJOM30年 |
首藤 傳明 |
| 成長を続けるNAJOM |
シェリル・コール |
| 経絡について―臨床の立場から― |
形井 秀一 |
| 経絡 |
水谷 潤治 |
| 感情の状態を表す経絡 |
ボブ・クイン |
| なぜ経絡研究がライフワークになったか |
斎藤 哲朗 |
積聚治療入門Part26
経絡と積聚治療 |
高橋 大希 |
私の考える経絡試論
藤木俊朗の世界をベースに-Part 1 |
戸ヶ崎 正男 |
| 経絡はホンモノ 気もホンモノ |
トーマス・ソレンセン |
| 息を分ける-治療の紐を解きほどく経穴と経絡 |
アンソニー・トッド |
| 霊枢/経筋第13篇と第47篇「蔵象と体表との考察」 |
Z・ローゼンバーグ、S・コーワ |
経絡とは何か?
氣の生理学と脈診、および三氣に対する鍼法 |
足立 繁久 |
| 経絡論を支える古代東洋思想 |
久保田 直紀 |
鍼は刺さなくても効く
「皮膚は第3の脳」理論からの考察 |
松田 博公 |
| 婦人科治療と経絡 |
髙橋 正子 |
| ペアになってストレッチ |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 経絡気功 |
ジェイク・フラトキン |
| 井上恵理、本間祥白 共著 鍉鍼説明書の要約 |
スティーブン・ブラウン |
シリーズ操体–橋本敬三の臨床を再現するためのロードマップ 02
呼吸の力と連動 |
小松 広明 |
| 低周波鍼施術の右顔面麻痺への有効例 |
校條 由紀 |
近年のトルコでの地震後の
鍼による坐骨神経麻痺および橈骨神経麻痺の処置 |
ファルク・サヒン |
| 玉井天碧の「指圧法」:指圧のルーツを探る Part 11 |
スティーブン・ブラウン |
モクサアフリカ
南アフリカへ再上陸
お灸と共に粒鍼(耳シード)も! |
伊田屋 幸子 |
書評
深谷伊三郎:日本式灸療法の達人 |
シェリル・コール |
NAJOM セミナーシリーズNo.3
スティーブン・ブラウンによる首藤流経絡治療 |
サラ・バーグマン |
| ハワイでの岩岡博先生の操体・鍉鍼セミナー |
ジェフリー・ダン |
2023年イン・タッチジャパンセミナー
およびいやしの道セミナーの日程探訪 |
鈴木 マヤ |
| 追悼 神谷一信1943-2023 |
村下 智子 |
|
2023年11月 No 89
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
ジェフリー・ダン
ボブ・クイン |
| なぜ鍉鍼にはまってしまったか |
船水 隆広 |
| 鍉鍼道: 鍉鍼とは |
ボブ・クイン、ゼイ・カイ・ポウ |
| 母の手-鍉鍼 |
ジェフリー・ダン |
鍼は刺さなくても効く
「皮膚は第3の脳」
理論からの考察 |
松田 博公 |
| 鍉鍼の経絡治療への適応 |
トーマス・ソレンソン |
| 臨床で鍉鍼を活用するためのモジュール式方法論 |
ダニエル・シルバー |
| ストーニーブルック小児病院に鍉鍼を持って |
マーク・ペトルッジィ |
大腿痛を伴う月経痛の鍼灸
新デルマトームに鍉鍼を併用して |
髙橋 正子 |
| ドクターベア流の鍉鍼 |
岩品 太盛 |
| 積聚治療入門Part25_ 鍉鍼 |
高橋 大希 |
| 古代鍼について |
森岡健介、藤本新風 |
| 鍉鍼のタッピング |
猪飼 祥夫 |
リスニングポストとしての
鍉鍼からの教訓 |
ゲリー・クレッパー |
| 鍉鍼による素朴で簡単な治療法 |
岩下 秀明 |
| 鍉鍼ケーススタディ: 夜驚症 |
ローレン・ヘイス |
| 私の鍉鍼、私の魔法の杖 |
ミッチェル・ ウルフ |
| A User's Guide to the Teishin and Enshin |
オラン・キヴィティ |
| 身辺雑記 |
首藤 傳明 |
| 患者自身が驚いた症例 |
形井 秀一 |
| 五十肩タイプの頸部神経根症 |
長田 裕 |
橋本敬三の臨床を再現するためのロードマップ(1)
運動系の連動 |
小松 広明 |
| 慢性の腎臓病に対する鍼治療 |
ファルク・サヒン |
| 近代日本鍼灸の歴史 最終回 |
東郷 俊宏 |
| 水谷潤治の竹筒灸治療 |
スーザン・マノンギ |
| 訃報 ヴィンセント・フォルク |
ヤン・マン |
セミナーレビュー:
ジェフリー・ダン/ マーク・ペトルッツィとさらに深く |
ランディ・ルーカス |
|
2023年07月 No 88
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 驚くべき症例研究 |
マーリン・ヤング |
| 針が一番よく効く疾患は2番目は? |
首藤 傳明 |
| 眼窩内刺鍼の手技 |
猪飼 祥夫 |
| トラウマを抱えた子供たちへの小児鍼治療 |
トーマス・ヴェルニッケ |
| トゥレット症候群に対するPNST療法および鍼灸による施術 |
ラマン・カプール |
| 経絡治療の客観性Part2 |
中野 正得、宮脇 優輝 |
肛門性器および鼠径部痛症候群の治療
PNSTピンポイントシリーズ第10回目 |
長田 裕 |
| 首藤流臨床記 新型コロナ後遺症 |
村田 守宏 |
| 驚くような効果があった意外な症例(自分編) |
高橋 正子 |
| 肩の痛みと足の痛み |
水谷 潤治 |
| 均整灸による姿勢のバランス |
フィリップ・カウデット |
| 積聚治療入門Part24 症例 |
高橋 大希 |
| ラムゼイハント症候群に対する鍼灸治療 |
笠 律子 |
| ケーススタディあれこれ |
パメラ・E・ファーガソン |
| 脳卒中患者のYNSA処置における薬物干渉 |
ファルク・サヒン |
| 新型コロナワクチンの薬害症状で知っておくべきことは? |
小松 広明 |
| 日本における美容鍼灸旋風 |
北川 毅、マクギバン・美登利 |
日本鍼灸史Part8
戦後の日本鍼灸 現代医学と古典のはざまで |
東郷 俊弘 |
玉井天碧の指圧法
指圧のルーツを探るPart10 |
スティーブン・ブラウン |
| 高橋英夫先生の日本式腹診セミナー |
サラ・バーグマン |
| 桑原光栄先生の最後のワークショップ |
グレッチェン・ローレンソ |
| 書評:Afterglow 相火と中国生態医学 |
ジョン・コッコ |
|
2023年03月 No 87
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 現代鍼灸の伝統と革新 |
ジェフリー・ダン、マーク・ペトルッツィ |
| 日本鍼灸師会愛知学術大会講演part1 |
首藤 傳明 |
| 経絡治療の客観性part1 |
中野正得、宮脇優輝 |
| PNSTの長い旅 |
長田 裕 |
| 鍉鍼にのめり込む |
ボブ・クイン |
| 打鍼の真価 |
高橋 英生 |
| お灸馬鹿のひとり言 |
水谷 潤治 |
| 子ども視点で世界をみる |
小松 広明 |
積聚治療入門part 23
はまっている治療法 |
高橋 大希 |
| 訃報 福島哲也・石原克己先生 |
水谷 潤治 |
| 刺絡と私 |
友部 和弘 |
| ペアになってストレッチ!動きましょう! |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 可能性が広がる新しい治療音叉療法 |
山本 真澄 |
| 鍼の学び方 私の出会った先生方 |
水谷 潤治 |
| 古(いにしえ)の仙人と現代の科学者の教え |
ブレンダ・ロー |
| 師匠の仕事を見学する |
石塚 浩太 |
手根管症候群の治療
PNSTピンポイントシリーズ第9回目 |
長田 裕 |
| 脳卒中後失語症の処置 |
ファルク・サヒン |
| 言語障害と嚥下障害の鍼治療 |
猪飼 祥夫 |
| 不妊症に対する鍼灸治療 |
橋 正子 |
玉井天碧の「指圧法」
指圧のルーツを探るPart 9 |
スティーブン・ブラウン |
モクサアフリカ
南アフリカへ再上陸 |
伊田屋幸子 |
| 新型コロナ後遺症のお灸100日間チャレンジ |
マーリン・ヤング |
ハイデザート・ハリ・ソサエティでの
刺絡セミナーの所感 |
ゲイリー・クレッパー |
|
2022年11月 No 86
|
詳細
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 居酒屋での語らいの中から |
形井 秀一 |
| 素晴らしい指導者達 |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 一期一会の師匠との出会い |
スティーブン・ブラウン |
| 師匠を追い続けて |
原 オサム |
積聚治療入門 Part22
師匠の仕事を見学する |
高橋 大希 |
| 小林詔司 1942-2022 |
ティシャ・マロン |
| 師匠の仕事を観察する |
山田 勝弘 |
スティーブン・バーチ
鍼灸界で最も輝かしい人物 |
オラン・キビティ |
| 達人達と鍼灸の修得 |
トン・バン・フフェレン |
伝統の火を引き継ぐ
クオン・ダウォン |
ピーター・エックマン |
| 師はもっとも必要とする時、現れる |
ボブ・クイン |
| 岩品安柳 1949-2022 |
和田 雅子 |
40年間の鍼、指圧、漢方
地図にない私の遍歴 |
ナイジェル・ドーズ |
| 技の伝承と発展について |
福島 哲也 |
| 現代の深谷灸師、福島哲也 |
フェリップ・カウデット |
| 私の三師匠の思い出 |
久保田 直紀 |
| 師匠に従事したユニークな経歴 |
トーマス・ダックワース |
| 師匠の仕事を見学する |
奥村 裕一 |
| 鍼灸木漏(こも)れ日 Part-7 |
首藤 傳明 |
| 簡単で効果的な経筋治療の応用 |
手嶋智子、篠原昭二 |
| PNSTによるピンポイント治療 Part 8 |
長田 裕 |
| 産科の灸治療 |
田川 健一 |
| Overtone resonance pillowの臨床応用 |
安士 正人 |
| 赤ちゃん、子供の頭の治療とホームケア Part2 |
小松 広明 |
| 更年期障害の鍼灸治療 |
高橋 正子 |
| 玉井天碧の「指圧法」 指圧のルーツを探る Part8 |
スティーブン・ブラウン |
日本鍼灸史 Part7
近代における古典鍼灸の復興 |
東郷 俊宏 |
モクサアフリカの
お灸100日間チャレンジの中間集計 |
マーリン・ヤング |
日本の伝統的な鍼灸治療と
オステオパシー・マニピュレーションとの融合 |
サラ・E・リヴキン(任昕蕾) |
|
2022年07月 No 85
|
詳細
|
在本 |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 鍼灸、指圧、漢方による顎関節症治療例 |
ナイジェル・ドーズ |
| お灸・筋肉、そして、はかり知れないもの |
フェリップ・カウデット |
| 操体について考える |
ジェフリー・ダン |
| 動きと陰操体 |
ボブ・クイン |
| 嗚呼、その筋肉と骨よ! |
パメラ・ファーガソン |
| 腰痛と腹のしこり |
高橋 英生 |
| 赤ちゃん、子どもの頭の治療とホームケアPart1 |
小松 広明 |
| 新しい経筋治療の勧め |
篠原 昭二 |
直接灸以外の
お灸で筋緊張部位への面的アプローチ |
福島 哲也 |
| 筋経と武術 |
本多 進 |
積聚治療入門 Part21
意識の使い方 |
高橋 大希 |
ホリスティック治療の一症例
強直性脊椎炎 |
ファルク・サヒン |
| お灸マッサージ |
水谷 潤治 |
| 鍼灸木漏(こも)れ日 Part-6 邪気論 |
首藤 傳明 |
| 灸は、新型コロナウイルス感染症後遺症に効くか? |
マーリン・ヤング |
Sei-ki/精気に関するマニフェスト
タッチの革命 |
アリス・ウィールドン |
| 月経不順の鍼灸治療について |
高橋 正子 |
| 私の見習い時代のこと |
キャロル・ウェインガルテン |
| 世界最古の経脈人形 |
猪飼 祥夫 |
日本鍼灸史 Part6
近代(明治維新~終戦) |
東郷 俊宏 |
| 玉井天碧の「指圧法」 指圧のルーツを探る Part7 |
スティーブン・ブラウン |
書評
日本鍼灸の極意 管鍼法 |
シェリル・コール |
セミナーレポート
経絡治療での温竹灸 |
ダニエル・ジッザ |
セミナーレポート
Ehrland Truitt氏による脈診と刺鍼法セミナー |
キンバリー・マロニー |
セミナーレポート
ナイジェル・ドーズ氏による津液証の漢方治療 |
チャーリー・ニューベリー |
|
2022年03月 No 84
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 『養生訓』の教え |
エリック・マイケルセン |
| 「治る力を信じる」ということ |
形井 秀一 |
| 患者のセルフ灸について |
マーティン・ハーマン |
| マスク着用生活と口呼吸の落とし穴 |
小松 広明 |
| 患者に勧めること |
水谷 潤治 |
回復への道
患者のセルフケア |
トーマス・ダックワーズ |
| クライアントのセルフヘルプ戦略 |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 2型糖尿病の鍼とセルフケア |
バート・ウォルトン |
ミニ症例報告
歯槽膿漏 |
藤川 直孝 |
| 緑内障の家庭療法とその次に来るもの |
トンヴァン・ハフェレン |
自宅での施灸指導から
睡眠の質が向上した症例 |
谷田 保啓 |
| 頻尿の三針法と運動療法 |
猪飼 祥夫 |
| 生理痛の鍼灸治療とセルフケア |
髙橋 正子 |
新型コロナ後遺症のお灸
100日間チャレンジ |
マーリン・ヤング |
| 鍼灸木漏(こも)れ日 Part-5 |
首藤 傳明 |
クアンタム指圧について
ベス・ハザード鍼灸師のインタビュー |
ボブ・クイン |
| 舎岩鍼法と経絡論 |
フィリップ・スージャー |
| 耳介療法 Part 4 |
藤川 直孝 |
| PNSTによるピンポイント治療 Part 7 |
長田 裕 |
| 陰虚のシステムズバイオロジー |
山岡 傳一郎 |
積聚治療入門 Part20
コロナ関連の症例 |
高橋 大希 |
| 体表の観察 |
小林 詔司 |
| 片頭痛のホリスティック処置 |
ファルク・サヒン |
日本鍼灸史 Part5
江戸時代 後編 |
加畑 聡子 |
| 玉井天碧の「指圧法」 Part6 |
スティーブン・ブラウン |
|
2021年11月 No 83
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール、水谷潤治 |
| 鍼灸による免疫調節 |
塚本 紀之 |
| 五行、衛気営血弁証、三焦 |
ロバート・ハイデン |
| 養生灸のすすめ |
福島 哲也 |
| 免疫雑感 |
水谷 潤治 |
伝統的方法を用いて
身体の免疫力を強化する法 |
久保田 直紀 |
| IBS と脳腸相関 |
校條 由紀 |
| 免疫系のサポート |
パメラ・ファーガスン |
| 免疫システムの安全防護策 |
トーマス・ダックワース |
| 重症筋無力症の治療 |
マーティン・ハーマン |
症例研究
若年性関節リウマチ |
ファルク・サヒン |
| シェーグレン症候群と操体 |
小松 広明 |
| N灸(電子灸)による白血球増強効果について |
中村 辰三 |
| 帯状疱疹後神経痛を電子灸を使い施術した症例 |
藤川 直孝 |
| 外感熱病・花粉症 |
山田(深澤)智子 |
| 新型コロナ後遺症 |
マーリン・ヤング |
| Long COVIDへの治療戦略 |
山岡 傳一郎 |
| デルタ変異株ヨーロッパ紀行 |
ボブ・クイン |
鍼灸木漏(こも)日
Part-4 |
首藤 傳明 |
| こころの病に対するTST鍉鍼術による治療法Part2 |
船水 隆広 |
| 回顧録:高野美加先生 |
オラン・キヴィティ |
| PNST によるピンポイント治療Part 6 |
長田 裕 |
| ナソ領域への探検 |
アミチャイ・サレーフィッシュバッハ |
| 積聚治療入門 Part 19 未病 |
高橋 大希 |
日本鍼灸史 Part4
江戸時代前期 |
加畑 聡子 |
| 玉井天碧の「指圧法」 Part5 |
スティーブン・ブラウン |
|
2021年07月 No 82
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 心と体:二つで一つ |
ナイジェル・ドーズ |
| こころを按ずる |
高橋 英夫 |
| こころの病に対するかね鍉鍼治療 Part 1 |
船水 隆広 |
| トラウマを解消する目の育て方 |
小松 広明 |
| 気滞と督脈上の障害物 |
福島 哲也 |
| 心理的治療における虚里の使用 |
イヴァン・ベル |
| 胸骨で心の治療 |
シンシア・クワットロ |
無形の経験:
不安障害に対する鍼灸と
トークセラピーの組み合わせ |
マーティン・ハーマン |
生理前に発症する舌痛に対する
漢方処方・鍼治療 |
山田(深澤) 智子 |
| ストレスはニューノーマル |
パメラ・エレン・ファーガスン |
| 百会の力 |
猪飼 祥夫 |
指圧と認知症:
オーストラリアでの研究プロジェクト報告 |
アンドリュ・コース |
すべり症と診断されて
頻脈になった症例へのお灸の効果 |
校條 由紀 |
| ワクチン副作用の省察(抄訳) |
ルカ・ペラ |
| Coronavirus Update |
本多 進、浅原 由江、角谷 瑞穂 |
| 鍼灸木漏(こも)れ日 Part 3 |
首藤 傳明 |
| PNST による治療Part 5 |
長田 裕 |
| 精神疾患について |
高橋 大希 |
| 紫雲膏の作り方 |
水谷 潤治 |
耳介療法 Part 3
耳介療法と体鍼で痩せた症例 |
藤川 直孝 |
| 片頭痛のホリスティック処置 |
ファルク・サヒン |
日本鍼灸史 Part3
鎌倉・室町時代の鍼灸医学史 |
島山 奈緒子 |
| 玉井天碧の「指圧法」 Part 4 |
スティーブン・ブラウン |
書評:
温竹メソッドによる平田式反応帯療法 |
ブレンダ・ロー |
書評:
指圧治療で死と喪失に対処する |
シェリル・コール |
書評:
いのちのエネルギー医学 |
ジェイソン・R・ハックラー、
メリー・ワリス、
テッド・ホール |
|
2021年03月 No 81
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 追悼 ピーター・イエーツ |
NAJOM 会員 |
| 追悼 高野美加先生 |
廣長 愉美 |
| 医療の陰と陽 |
マーリン・ヤング |
| 陰陽に触れる |
ボブ・クイン |
| 経絡理論のミッシングリンク |
フィリップ・スージャー |
臨床に役立つ
日々の感覚みがき |
小松 広明 |
| 陰と陽 私見 |
水谷 潤治 |
| 臨床にみる陰陽観 |
小林 詔司 |
| 陰陽論-医学, 物理学, 哲学 |
ファルク・サヒン |
| 統一された陰と陽 極性の超越 |
ニニ・メルヴィン |
| 積聚治療入門 Part 17/Part 16 |
高橋 大希 |
| 三賢によるレッスン |
久保田 直紀 |
| 陰陽理論を用い適切な治法を導き出すためには |
山田 智子 |
| PNST/陰陽/自律神経系 |
ラマン・K 他 |
| PNST による治療Part 4 |
長田 裕 |
| 花粉症・鼻炎に対する「鼻うがい」効果 |
長田 裕 |
| コロナウイルスに対する緊急提言 |
長田 裕 |
システムズバイオロジーからみた
COVID-19 への戦略Part 3 |
山岡 傳一郎 |
| 片麻痺患者に対する積聚治療 |
山内 英生他 |
| 鍼灸木漏(こも)れ日 Part 2 |
首藤 傳明 |
| 平田氏12反応帯と温竹メソッド |
オラン・キヴィティ |
| Eye 灸とクリアパイプ灸 |
本多 進 |
| 腰下肢痛に対する耳介療法 |
藤川 直孝 |
| 腰痛の治療法について |
澤口 博 |
映画撮影現場における
コロナウィルス感染予防対策 |
チャーリー・ニューベリー |
| 江戸時代のお灸 |
市川 敏男 |
| 玉井天碧の「指圧法」 Part 3 |
スティーブン・ブラウン |
Book review
腹診と漢方 |
ピーター・イエーツ |
|
2020年11月 No 80
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 七転八起 |
ジーン・カー |
| 癌生存者としての旅 |
パメラ・ファーグソン |
| 東アジアの医療が私の人生を変えてくれた |
アーランド・トルイット |
| 難しい症例より得られた教訓 |
船水 隆広 |
| 癌治療を受けている患者との人生の旅 |
前田 篤希 |
| 深刻な医学的試練の経験から学んだこと |
ジョン・ディクソン |
| 困難な治療より得られた洞察 |
石原 克己 |
| 老化という病への鍼灸治療 |
校條 由紀 |
| 積聚治療入門Part16 |
高橋 大希 |
| COVID-19と交差免疫 |
安士 正人 |
システムズバイオロジーからみた
COVID-19への戦略 |
山岡 傳一郎 |
宿主免疫、お灸、
長期新型コロナウイルス感染症の
脅威について |
マーリン・ヤング |
| COVID後合併症に対する鍼治療 |
ラーマン・カプア |
| Covid-19 Update |
ピーター・エックマン その他 |
| コロナウイルス in Tokyo |
本多 進 |
| 打膿灸の成り立ちと展開 |
谷田 保啓 |
| 打膿灸の施灸方法 |
谷田 保啓 |
玉井天碧の「指圧法」
指圧のルーツを探る |
スティーブン・ブラウン |
| 生氣操法について |
ボブ・クイン |
| 音叉療法 |
山本 真澄 |
| 鍼灸 木漏(こも)れ日 |
首藤 傳明 |
症例報告
副腎皮質ホルモン分泌低下症 |
澤口 博 |
耳針法その1
腫瘍特導区について |
藤川 直孝 |
| PNST によるピンポイント治療 Part3 |
長田 裕 |
| アトピー性皮膚炎に対する鍼治療 |
山田 智子 |
| 最近の症例 |
高嶋 正明 |
| 書評 山元式新頭鍼療法 |
ジョージ・チャチス |
| モクサアフリカニュース |
マーリン・ヤング |
|
2020年07月 No 79
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
自分の経験から
インフルエンザの治療を考える |
水谷 潤治 |
システムズバイオロジーからみた
COVID-19への戦略 |
山岡 傳一郎 |
| 結核と新型コロナウイルスの比較対照 |
マーリン・ヤング |
COVID-19
伝統医学と近代医学の見知から |
石原 克己 |
| コロナウイルスと鍼灸 |
形井 秀一 |
| ウィルス性疾患の鍼治療 |
ファルク・サヒン |
コロナウイルス
パンデミック中の睡眠障害 |
シンシア・クアトロ |
| 料理医学でCOVID と戦う |
レスリー・スミス
タヌジャ・アラニー
コリー・マイヤーズ |
| インフルエンザの発熱に刺絡 |
猪飼 祥夫 |
新型コロナ感染症に対する私見と私院での取り組み
北辰会方式 |
村田 守弘 |
| COVID-19で蔓延している不安にどう向き合っていくのか? |
小松 広明 |
| パンデミックにおける診療 |
パメラ・ファーガソン |
| ロックダウンから思うこと |
オラン・キビティー |
| Dr Shi'sのセルフ・マッサージ |
バート・ウォルトン |
| 刺絡の歴史と現代刺絡療法 |
友部 和弘 |
| 深層指圧より深い経絡とのコミュニケーション |
テッド・トーマス |
| 玉井天碧の指圧法 |
スティーブン・ブラウン |
| 逆子の鍼灸治療の症例報告 |
形井 秀一 |
| 北辰会方式による卒腰痛の一症例 |
藤本 新風 |
澤田流の太極療法
Part-2 |
山田 勝弘 |
PNST によるピンポイント治療
Part2 |
長田 裕 |
| PNST の有効性:臨床例 |
ラマン・カプア |
| 難治性吃逆の一症例 |
関 功芳 |
| 積聚治療入門 Part15 |
高橋 大希 |
| オラン・キビティの全治療体系が出版された |
ボブ・クイン |
| 漢方セミナーレポート |
グレッグ・スキャンロン |
|
2020年03月 No 78
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 糖尿病の鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
糖尿病による
抹消神経障害への鍼灸の有効性 |
C. レスリー・スミス |
メタボリックシンドローム
伝統日本鍼を用いた現代病の治療漢方とは? |
シンシア・クアトロ |
| 脳梗塞後の疼痛に対し、一貫堂処方と刺絡が奏功した一例 |
小川 恵子 |
| 消渇の名灸穴 |
福島 哲也 |
耳ツボ検証
飢点刺激は体重増加を抑える |
校條 由紀 |
| 糖尿病の鍼灸治療の生情報 |
鈴木 育雄 |
日本鍼灸史 Part 2
平安時代の鍼灸医学史 |
島山 奈緒子 |
| 打鍼術について |
藤本 新風 |
| 北辰会方式 |
藤本 新風 |
| 澤田流の太極療法 |
山田 勝弘 |
| 灸頭皮内鍼 |
アーロン・ルービンステイン |
| 積聚治療 |
高橋 大希 |
| 首藤流鍼灸術 |
村田 守宏 |
| 系統的経絡治療 |
トーマス・ソレンセン |
Tama Touch©:
奇経に作用するHand-Kiメソッド |
マリー・S・ウォリス |
| PNSTによるピンポイント治療 Part1 |
長田 裕 |
PNST感謝祭
和歌山にて長田先生と |
ボブ・クウィン |
| 澤田流太極療法を基本にした鍼灸臨床 |
山田 勝弘 |
| Perfect Clean Needle Technique |
猪飼 祥夫 |
| モクサアフリカ・レポート |
マーリン・ヤング |
山元式新頭皮鍼
アメリカ西海岸・初セミナー |
田中 康夫 |
セミナー・レポート
操体Intuitivo |
ボブ・クウィン |
2020 腰バランス テクニック
イギリスで二回目のセミナー |
ジェス・バーミングハム |
| すべての道はローマに通じトリノに集う |
マルコ・スペルビ |
In Touch Japanセミナー
鍉鍼 |
アイザック・マン・シルバーマン |
In Touch Japanセミナー
東方会接触鍼 |
ジェフリー・ダン |
In Touch Japanセミナー
首藤流経絡治療 |
バヴナ・ダジア
トーリー・シンク |
2019 WHO-FIC
ネットワーク・ミーティング |
斉藤 宗則 |
|
2019年11月 No 77
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 奈良時代以前の鍼灸医学史 |
猪飼 祥夫 |
今号のテーマに関して:
日本鍼灸とは? |
水谷 潤治 |
| 漢方とは |
清野充典・鶴崎孝昌 |
| 管鍼術の創始と確立 杉山流について |
大浦 慈観 |
| 体質調整鍼 |
ピーター・エックマン |
| 大師流小児はり |
館坂 聡 |
| ドクターベアースタイルの鍼療 |
岩品 安柳 |
| 深谷灸 |
フェリップ・コウデット |
| 石坂流鍼術 |
久保田直紀 |
| 松本岐子流鍼灸 |
グレース・ロリンス |
| コトタマ・ライフ・メディスン |
トーマス・E・ダックウォース |
| 水谷式竹筒灸法 |
水谷 潤治 |
| 向野メソッド |
伊田屋 幸子 |
| 温竹灸について |
高野 美加 |
| TAKAHIRO STYLE TECHNIQUE(TST) |
船水 隆広 |
東方会の治療
鍼によって「気」を動かす |
津田昌樹・小川恵子 |
| 東洋はり経絡治療の概要 |
ダニエル・ジッザ |
| 陰操体: 歪みを正す |
ボブ・クウィン |
| 禅指圧という旅 |
パメラ・エレン・ファーガスン |
積聚治療入門Part14
外傷について その1 |
高橋 大希 |
| 神経変性疾患と重金属の役割 |
ファルク・サヒン |
モクサアフリカ
北朝鮮での2回目のお灸 |
マーリン・ヤング |
船水隆広
鍉鍼セミナー |
高山 清香 |
|
2019年07月 No 76
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| NAJOM25周年記念大会 |
アーランド・ツルーイット |
| スティーブン・バーチ 東洋はりの真髄 |
デービッド・ハーマン |
| 船水隆広先生: 鍼のジェダイ |
ダニエル・シルバー
シェリル・コウル |
| ラウンドロビンでさまざまな治療法を一度に体験 |
シェリル・コウル |
| 経穴は効かすもの |
シェリル・コウル |
| 水谷潤治と施しの医術 |
エレイン・マーフィー
シェリル・コウル |
| 日々変化する世界の持続可能な医療について話をする時がきた |
マーリン・ヤング |
| 神経科学:骨髄の髄 |
アシュレー・クラッチフィールド |
| 認知症と慢性神経系炎症 |
シンシア・クアットロ |
| 認知症の予防法 私の場合 |
水谷 潤治 |
| 「ツボ」と「お灸」を使った健康講座の試み |
福島 哲也 |
| 認知症と百会の灸 |
猪飼 祥夫 |
| 認知症の人への鍼灸治療 |
校條 由紀 |
| 薬物を使用しないパーキンソン病の処置 |
ファルク・サヒン |
| 生気を保つ |
大西 真由 |
| 認知症の鍼灸治療について |
高嶋 正明 |
| 雲の影に蔽われた: 錬丹術の変化過程心と体の繋がり |
ヤニブ・リヒター |
| うつ病の鍼灸治療 |
小窪潤蔵 |
| 体表所見から何が捉えられるか Part 2 |
戸ヶ崎 正男 |
| 皮膚の仕組みとイオンパンピングコード(2) |
本多 進 |
| 沢田流小論 |
水谷 潤治 |
| 陰陽医学としての操体考察 |
ボブ・クウィン |
| 私とお灸 |
高野 美加 |
| 回路を基に考える五臓六腑と経絡の関係 |
フィリップ・スージャー |
| 積聚治療入門Part 13 |
高橋 大希 |
| 腹診:漢方における腹診の役割 Part 5 |
ナイジェル・ドーズ |
| 書評:Heal Yourself with PNST |
細山田 紀子 |
|
2019年03月 No 75
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| NAJOM25周年祝辞 |
首藤 傳明 |
| 首藤傳明先生とNAJOM |
水谷 潤治 |
| 鍼灸と皮膚についての考察 |
スティーブン・バーチ |
| 体表所見から何が捉えられるか |
戸ヶ崎正男 |
| 指頭感覚について:修得するために必要なこと |
松林 康子 |
皮膚の仕組みとイオンパンピングコード
Part1 |
本多 進 |
| 皮膚観察に基づく日本伝統鍼灸 |
津田 昌樹 |
| 皮膚炎を促す |
高橋 英生 |
| 墨灸 伝統的な小児の治療 |
猪飼 祥夫 |
| 筋膜と深谷灸 |
フィリップ・カウデット |
| 尺膚診 |
福島 哲也 |
| 皮膚は体の健康状態を映し出す |
ラン・カリフ |
| 触診について |
笠 律子 |
| 歩行痛があるイボのお灸 |
高野 美加 |
| 生命力の鏡 |
メリー・ウォーリス |
| うつ病・うつ症状の考え方と臨床 Part 2 |
石原 克己 |
| 心と体の繋がり Part 2 |
山田 勝弘 |
| 動物達が教えてくれた感情と身体の繋がり |
鈴木 万記子 |
| 火と木の少陽歌 顕在意識と潜在意識のつながり |
エラド・イザコブ |
| 鍼灸と精神-体の関係性 |
ジョン・ディクソン |
| 漢方における腹診の役割 part 4 |
ナイジェル・ドーズ |
| フィールド |
ボブ・クウィン |
| 積聚治療入門Part 12 |
高橋 大希 |
| 散鍼で急性腰痛を治療した一例 |
和田 雅子 |
灸頭皮内鍼 温灸皮内鍼テクニック Part 7
ベル麻痺治療 |
アーロン・ルービンシュタイン |
| モクサアフリカと多剤耐性結核 |
マーリン・ヤング |
| 2018年 ジャパン9セミナー(東京/四国)レビュー |
ジュディス・トンプソン |
セミナーレポート
Kiiko Matsumoto Japan Study Seminar |
グレース・ロリンズ |
| ハイデザートはり協会はりキャンプ |
クラウディア・シールズ |
首藤流経絡治療
村田守弘先生とスティーブン・ブラウン氏 シアトルにて |
KC・コノバー |
|
2018年11月 No 74
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| がん患者を診る |
ピーター・エックマン |
| 心と体の繋がり Part-1 |
山田 勝弘 |
| 心身相関と鍼灸 |
船水 隆広 |
| うつ病・うつ症状の考え方と臨床 Part 1 |
石原 克己 |
| 精神的ストレス・心の病の治療穴 |
福島 哲也 |
| 鬱と病理的エネルギー |
高橋 英生 |
| 東洋と西洋・心と体 一体的医学への考え |
ボブ・クイン |
| 心身相関を感じる智恵と勇気を育てること |
トン・ファン・フフェレン
ミリヤム・ファン・フフェレン |
| 確かなこと |
高松 文三 |
| マインドフルで、実践的、そしてクリエイティブ |
パメラ・エレン・ファーガスン |
| ただの心 |
ファルク・サヒン |
| 嫁姑問題と脳の興奮 |
校條 由紀 |
| お灸の時間がもたらすもの |
高野 美加 |
| 一症例から考える心身相関 |
高嶋 正明 |
| 腹部の解剖学に基づいた治療法 |
ジェフリー・ダン |
| 深谷先生と縄折法 |
フィリップ・カウデット |
| 仁丹の歴史と新しい臨床活用法 |
安士 正人 |
| 自律神経失調症からくる背部痛 |
鶴田真一 |
| 音叉治療について |
山本 真澄 |
| 積聚治療入門Part 11 |
高橋 大希 |
| 難治の慢性血管性浮腫:2つの症例 |
ヤニヴ・リッチター |
| 腹証のパターンと薬草の処方 |
ナイジェル・ドーズ |
| 繰体サミット 2 |
ボブ・クウィン |
| モクサアフリカレポート2018年9月 |
マーリン・ヤング |
| 船水隆広先生の鍉鍼セミナー |
角谷 瑞穂 |
| ハリスタイル鍼灸レポート |
ジョン・ダラー |
| トーマス先生の鍉鍼セミナーを振り返って |
佐々木 浩規 |
|
2018年07月 No 73
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・クール |
| 凡人による癌患者への灸治療 |
福島 哲也 |
| 癌患者の治療を考える |
水谷 潤治 |
| ガン患者に対する鍼灸治療 |
高嶋 正明 |
| お灸とガンについての一考察 |
マーリン・ヤング |
| ガン治療: 先生はどちら? |
ジェフリー・ダン |
| 癌患者への慎重な治療法 |
バート・ウォルトン |
価値あるものは傷つきやすい
ガン治療における鍼灸 |
トン・ヴァン・ハフレン |
| 癌に対する鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
| 癌治療の体験より |
笠 律子 |
| がん治療をサポートする |
マータブ・バヤット |
| ガンの治療について |
校條 由紀 |
| 日本鍼灸と触診(3) |
形井 秀一 |
腹診 Part 2
腹部の診察 |
ナイジェル・ドーズ |
人の中に疾患を診る日本鍼灸
Part-2 |
中根 一 |
積聚治療入門
Part10 |
高橋 大希 |
| 自己免疫疾患の処置に対する全人的アプローチ |
ファルク・サヒン |
| バネ指 |
大西 真由 |
| 自灯明 |
高松 文三 |
モクサアフリカ
北朝鮮レポート |
ユーリック・バーク |
東京代々木公園
アースデー |
伊田屋 幸子 |
全5回セミナー
嶋村流長野式 |
ボブ・クイン |
オレゴン州・ポートランド
日本式治療に乾杯! |
ボブ・クイン |
ドクターベアー
岩品安柳先生のポートランドセミナー |
ダニエル・シルバー |
| バークレー春季積聚治療研修会 |
アンナ・K・スミス |
| ケニア奥地の農村での医療キャンプにおける鍼灸治療 |
坂光 信夫 |
|
2018年03月 No 72
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 乳癌から多発性癌への蜂針治療と針灸治療 |
猪飼 祥夫 |
がんの化学療法の副作用による
手のしびれを訴えた一例 |
津田 昌樹 |
| 自然が意図する治療 |
高橋 英生 |
| 刺絡と頑固な慢性痛の症例 |
シャノン・キング |
| 皮質盲の鍼治療 |
ファルク・サヒン |
| 未妊症( 不妊症)の一症例 |
関 功芳 |
指圧と動きの関係で五行を調和する
2つの症例 |
パメラ・エレン・ファーガスン |
| トリガーポイントにお灸をしてみよう |
高野 美加 |
足の両側性の特発性ニューロパチー
神経炎 |
ラン・カリフ |
| 妊活お灸療法 |
ジェス・バーミンガム |
| 治療は西洋医学だけではない! |
八巻 美知子 |
現代医学(西洋医学)では対応できなかった症例
無名穴を中心に |
藤川 直孝 |
| 首藤流鍼灸術を用いた症例 |
村田 守弘 |
日本鍼灸
風土と人の中に疾患を診る(1) |
中根 一 |
日本鍼灸と触診 (2)
鍼灸における触れることの意味 |
形井 秀一 |
Part 1
漢方治療における腹診 |
ナイジェル・ダウェス |
大師流小児鍼法
小児治療と触診技術について Part 2 |
舘坂 聡 |
2018 池田政一先生による古典の知恵
人跡未踏の道 |
アラン・ジャンソン |
3レベル鍼灸プロトコル
ミキ・シマ氏の身体-耳セラピー |
ジェイク・フラトキン |
| 伝統医学と先進医療をクリニックで併用する |
トム・インゲグノ |
灸頭皮内鍼 Part 5
温灸皮内鍼テクニック |
アーロン・ルービンシュタイン |
| 日本の視覚障害者に対するあはき教育 |
ジョン・ディクソン |
| 2018年のモクサアフリカ名前が意味するものとは |
マーリン・ヤング |
| ポートランドでの小児鍼ダブルパンチ |
ボブ・クイン |
| 2017 ボストン積聚治療セミナー |
スザーン・リエンドー |
|
2017年11月 No 71
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 日本鍼灸と触診(1) |
形井 秀一 |
| 百見は一触に如かず |
福島 哲也 |
| 触診治療 |
水谷 潤治 |
| 鍉鍼術と触診術 |
船水 隆広 |
| 腹部の診察による気血津液弁証の検証法 |
宮川 浩也 |
| 触れるとは双方向交換である |
ボブ・クイン |
大師流小児鍼法
小児治療と触診技術について Part 1 |
館坂 聡 |
| 日本の鍼灸治療における触診の意味 |
大浦 慈観 |
| 目には見えない気を触知する |
岩下 秀明 |
| 触診と触れること |
高嶋 正明 |
| 脊椎を整える背部兪穴の秘密 |
鈴木 万記子 |
触診と治療
触診は慣れや経験が必要 |
校條 由紀 |
| 触診から見た経絡治療 |
品田 隆志 |
| 痛みを持つ患者に接する |
マリオラ・ストラルバーグ |
積聚治療
気を意識し、患部へ気を投射する |
山内 英生
藤原 典往 |
Part 3
十一鍼の紹介 |
石原 克己 |
日本における鍼と道具に関する考察
Part 3 |
大浦 慈観 |
課題と文化を回避した解決策
心経は治療できるのか? |
ジェフリー・ダン |
| 積聚治療入門 Part9 |
高橋 大希 |
| YNSA Z.S 点での閉経の処置 |
ファルク・サヒン |
10 年の道のりを歩んできたモクサフリカ
それはずっと奇妙な旅だった |
マーリン・ヤング |
セミナーレポート
鍉鍼−船水隆広 |
ユエン・ドング |
セミナーレポート
積聚治療 上級セミナー |
アンナ・スミス |
|
2017年07月 No 70
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| アンドリュー・フィッツチャールズを偲んで |
スティーブン・ブラウン
/ティシャ・マロン |
| 上なる如く、下もまた然り |
ボブ・クイン |
| We Need Your Help |
編集部 |
| 鍼灸医学による腹診 |
松本 弘巳 |
| 毒と邪気を目標とした腹診と鍼灸治療 |
大浦 慈観 |
| 腕踝針療法の実際 |
藤川 直孝 |
| 平田式熱鍼快療術 |
水谷 潤治 |
温竹療法を用いた
ホログラフィック・マッピングによる素早い疼痛治療 |
オラン・キヴィティ |
頭皮針と同時に四肢の運動を用いた
脳卒中後の偏片麻痺の処置 |
ファルク・サヒン |
ハッピー・フィート!
足が大喜び! |
パメラ・エレン・ファーガスン |
十一鍼の紹介
Part 2 |
石原 克己 |
日本における鍼と道具に関する考察
Part 2 |
大浦 慈観 |
| 積聚治療入門 Part8 |
高橋 大希 |
| 心身症の治療 |
猪飼 祥夫 |
2年以上鍼灸治療を施行した40歳以上
症例の予後 |
山内 英生
菊谷 大亮
藤原 典往 |
| モクサアフリカ 北緯38度線 |
ユーリック・バーク |
2017年第3回
国際お灸セミナー |
フェリップ・カウデット |
達人小林先生
積聚治療セミナー |
カレン・ヴァータニアン |
セミナーレポート
積聚治療について |
アーロン・ルービンステイン |
ドクターベアーのポートランドセミナー
優しいハリ・高度な鍼灸医術 |
ボブ・クイン |
レポート
宮脇優輝先生セミナーと治療体験 |
エレナ・ジウリニ |
書評
ピーター・デッドマン 「健康と長寿:中国式養生の伝統からの教え」 |
シェリル・コール |
|
2017年03月 No 69
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 鍼道具への思いと慢性ライム病治療 |
ボブ・クイン |
| 道具のビジネス |
ボブ・クイン |
| 収納クローゼットに入っているものは何か |
ジェフリー・ダン |
| 鍼とヤリガンナ |
高橋 英生 |
癒しの鍼具
シルバースミスの視点 |
マーク・パージンスキ |
十一鍼の紹介
Part 1 |
石原 克己 |
非刺入・接触系の鍼具について
鑱鍼(ざんしん)・圓鍼(えんしん)・鍉鍼(ていしん) |
福島 哲也 |
| 日本における鍼と道具に関する考察 |
大浦 慈観 |
| 小児はりの概要とその技法 |
井上 悦子
鈴木 信
横山 浩之
尾﨑 朋文 |
| 日本の鍉鍼術 |
船水 隆広 |
| 金の鍉鍼 |
高嶋 正明 |
| 経絡温竹パート3 |
オラン・キビティ |
| 温竹灸プロと鉄棒灸 |
本多 進 |
| 治療ツールとしての半導体ダイオード |
シェリル・コール |
| 鍼灸用具 売れ筋ランキング |
編集部 |
| 積聚治療入門 Part7 |
高橋 大希 |
| 素人がはまったお灸 |
萩原 朋子 |
モクサアフリカの日本「ツアー」
私たちを不安にさせた津波に対する思いと共に |
マーリン・ヤング |
Help Moxafrica Japan Project - November 2016
謝辞 |
水谷 潤治 |
ジャパン7 イン・タッチ国際鍼灸セミナー
レポート:2016 |
イレイン・マーフィー |
レポート
ケニア無料医療キャンプ |
坂光 信夫 |
ネパールにおける
脳梗塞後遺症の左片麻痺患者に対する鍼治療 |
児山 俊浩 |
|
2016年11月 No 68
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
アンドリュー・フィッツチャールス |
| 西洋の科学と東洋の治療 |
ミケル・マスグラウ |
| 東洋医学と西洋医学 独特で互角 |
ピーター・エックマン |
目指すところは昔と同じ
東洋医学と西洋医学の統合について |
キャトリーン・B・ヘゴルマン |
| 日本鍼灸の医療モデル |
ベンジャミン・CW・チャント |
入院患者への鍼診療提供
3カ月の試験期間から学んだこと |
レスリー・スミス
マリア・マルカヒイ |
カリフォルニアの最大手
ヘルスケア・プロバイダーでの仕事 |
アンドリュー・フィッツチャールス |
| 東西医学に相触れて |
田中 清 |
Q & A
イザベル・チェン・アングリカー医学博士の経験 |
イザベル・チェン
アングリカー・パメラ・エレン・ファーグスン |
脳外科医のチクチク療法
(無血刺絡療法) |
長田 裕 |
東洋医学の知恵を生かした治療
M-Test |
向野 義人 |
| うつに対する包括的なアプローチ |
バート・ウォルトン |
鍼とカイロプラクティックの組み合わせによる
多発性硬化症の処置 |
ファルク・サヒン |
| 鍼灸とCST における一考察 |
高嶋 正明 |
| 脳報酬系に対する鍼灸治療の影響 |
福田文彦、矢野忠、加藤麦、吉本寛司 |
按摩手掌軽擦法
最大筋力、筋持久力に対する効果 |
清水正輝、森北育宏 |
| 無感覚その2 |
霸麒 |
| 積聚治療入門Part 6 |
高橋 大希 |
身体的、精神的ストレスを伴う疾患に対する日本伝統鍼灸
積聚治療の効果 |
山内 英生
藤原 典往 |
桑原先生による
小児はりセミナー
ポートランド |
ボブ・クイン |
C コノバーによる疼痛治療セミナー
アラスカ州ホーマー |
ボブ・クイン |
操体法サミット
ボルダー2016 |
ジョー・ウォーレン |
| 村田守宏先生による首藤流経絡治療 |
アカジア・ギルモア |
鍼灸治療による支援活動
熊本地震/2016 |
リシン・マツミネ |
| 最後のルンビニヘルスキャンプ |
大澤 安則 |
|
2016年07月 No 67
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 慢性腰痛の鍼灸臨床を考える |
山田 勝弘 |
| 慢性疼痛を取り除く優しい手法-接触雀啄法 |
マーク・ペトルッツィ |
足底から頭皮へ
松本岐子スタイルを用いた痛みへの新治療法 |
グレース・ロリンズ |
慢性症状の鍼灸治療
毫鍼以外の鍼具活用のすすめ |
福島 哲也 |
| アルビ |
トーマス・ダックワース |
| 慢性痛と打膿灸 |
水谷 潤治 |
ケーススタディー
Ron(ステージ4、癌疼痛あり) |
マリー S. ウォリス |
石坂流鍼術と
酸アルカリ・陰陽食療による痛みの解消 |
久保田 直紀 |
| 慢性症状に対する経絡治療と黄帝様の言葉 |
品田 隆志 |
| 本治法と慢性全身痛 |
古江 崇 |
| ああ、偏頭痛ですか? |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 多次元現象としての慢性的な痛み |
マータブ・バヤット |
| 慢性疾患の症例 |
笠 律子 |
| 白蝋病 |
畑 美奈栄 |
| 慢性痛の症例 |
高嶋 正明 |
| デュピュイトラン拘縮と慢性痛の治療 |
武田洋樹
エリック・マイケルセン |
| 乳腺炎のお灸治療について |
高野 美加 |
| 膝関節腫痛 |
横田 観風 |
| 無感覚 その1 |
霸麒(Haki) |
| サリカ流 片手挿管法 |
サリカ・セルノハウス |
| 陰陽太極鍼の実際 |
吉川 正子 |
深谷灸法を理解するために
(パート2) |
フェリップ・カウデット |
積聚治療入門
Part5 |
高橋 大希 |
| 円皮鍼と経筋治療 |
藤川 直孝 |
| 嵐が丘ふたりの女性とその消えない不安 |
トンヴァン・ハフェレン |
| 乳癌摘出後の浮腫が鍼灸治療で軽減した例 |
校條 由紀 |
| 機能性ディスペプシアの一症例 |
関 功芳 |
| 積聚治療セミナーin サンフランシスコ2016 報告 |
田坂 里織 |
| スリランカの蝶相 |
パメラ・ファーグスン |
|
2016年03月 No 66
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
アンドリュー・フィツチャールス |
| 睡眠障害と不眠症の鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
| 不眠-千頭の手引き |
クリス・マカリスター |
| 証による睡眠状態 |
古江 崇 |
| 不安時代における睡眠について |
ダン・ジザ |
| 夢、鍼灸そして癒し |
ボブ・クイン |
少陰心経
少陰腎経の関係を使った、不眠と心虚治療の症例 |
ジェフリー・ダン |
| 不眠症の症例 |
水谷 潤治 |
| 睡眠は満足感が必要 |
校條 由紀 |
| 不眠について |
高嶋 正明 |
睡眠
天からの恩恵か禍か? |
イザベル・チェン・アングリカー |
| 不眠症への取り組み |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| よい睡眠と健康 |
大西 真由 |
| 幼少期の親子関係が体に刻まれています |
鈴木 万記子 |
| 症例報告 若年性関節リウマチの少年 |
ファルク・サヒン |
モクサアフリカReport
ビッグニュース |
マーリン・ヤング |
達人の治療見学
首藤治療院の一日 |
スティーブン・ブラウン |
積聚治療入門 Part 4
基本治療と補助治療 |
高橋 大希 |
| ドクターベアーメソッドを改めてご紹介します |
和田 雅子 |
| タンタン、モクモク、ヒョウヒョウ、ニコニコ |
高松 文三 |
越石 まつ江先生による
紫雲膏灸セミナー報告 |
ジョン・ディクソン |
| 日本ニカラグア東洋医学大学とWHOニカラグア |
八巻 晴夫 |
Report: In-Touch Acupuncture
日本鍼灸セミナー |
レザ・グナワン |
前之園空観先生による
いやしの道セミナー 於ブラジル |
テレサ・クサノ・ツカノ |
セミナーレポート
松本岐子 Japan Study Seminar 2015 |
グレース・ロリンズ |
関東東北豪雨災害における
鍼灸マッサージ支援活動の報告 |
三輪 正敬 |
|
2015年11月 No 65
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
| 澤田流太極療法の意義と特徴 |
山田 勝弘 |
| 深谷灸法の意義と特徴 |
福島 哲也 |
| 実際的灸療法 Part 38 |
水谷 潤治 |
深谷灸法を理解するために
パート1 |
フェリップ・カウデット |
臨床つれづれ
お灸の効能 |
八巻 美知子 |
関接灸の醍醐味
美しい光に包まれて |
岩下 秀明 |
| 未妊(fertility)・不妊治療、43歳の症例 |
高野 美加 |
灸治療における知熱灸と焼約灸の違いと
その適応疾患 |
校條 由紀 |
| 私が学んだお灸の捻り方 |
鈴木 ヘザー |
ウガンダ・カンパラのキスワ診療所における
お灸・結核研究 |
マーリン・ヤング |
| モクサアフリカ |
ユーリック・バーク |
視覚障害を持つ鍼灸師の伝統
視覚は妨げられない |
ジョン・ディクソン |
| 緑茶の素晴らしい効能 |
バート・ウォルトン |
| 鍼作用: 二つの観点 |
石田 安男 |
| 鍼による垂直とび、運動反射への影響 |
サラ・シェイファー
椿山清秀 |
| 脈診・触診とPDCA サイクル(2) |
宮川 浩也 |
| 積聚治療入門 Part 3 |
高橋 大希 |
| 脊柱の動きと奇経との間の関係性 |
ファルク・サヒン |
第30回
弦躋塾セミナーレポート |
笠 律子 |
第2回
東京温竹ワークショップの報告 |
竹本 光希 |
| サンタフェ- 岩品安柳セミナー |
デービッド・トゥーン |
| ウィーン 小児鍼セミナー |
首藤 順子 |
こころの不調
船水隆広氏によるセミナー |
シンシア・クワトロ |
| ネパール大地震報告 |
畑 美奈栄 |
|
2015年07月 No 64
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
アンドリュー・フィッツチャールス |
| 大師流小児鍼について |
上田 徳子 |
| 大師流小児鍼の治療効果 |
館坂 聡 |
| 小児はりを学び始めるきっかけ |
川瀬 邦裕 |
実際的灸療法37
小児灸 |
水谷 潤治 |
| 鍉鍼 考査と使い方 |
スティーブン・バーチ
井田 順子 |
| 魔法使いの棒でタッチ: 鍉鍼 |
トンヴァン・ハフェレン |
| 繊細な鍼灸用具のデザイン |
アントン・ウィルヘルム |
| 小児鍼の奇跡 |
カトリアンナ・ヘイジェルマン |
| 子どもとの接し方 |
首藤 順子 |
| ABによる子供にやさしいクリニックの設立 |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| Softly, Softly |
クリス・マカリスター |
| 小児鍼:成人治療への応用 |
ダニエル・シルバー |
| 鍉鍼と慢性ライム病治療 |
ボブ・クイン |
| 鍉鍼を用いた顔面部の施術方法 |
船水 隆広 |
| 小児治療の報告と虎口三関について |
品田 隆志 |
症例報告
積聚治療での小児強迫性障害の治療 |
エリック・ブルン |
| 行動問題のある子供を小児鍼で治療 |
マリアン・フィックスラー |
| 10代のサッカー外傷に対する本治療法 |
アシュリー・クラッチフィールド |
| 小児科における統合医療のあり方 |
イザベル・チェン・アングリカー |
| 脈診・触診とPDCAサイクル(1) |
宮川 浩也 |
積聚治療入門
Part 2 |
高橋 大希 |
| 毒と邪気の有り様をみる腹診法 |
大浦 慈観 |
| 2種類の胆経の症状にみる脈診の価値 |
マータブ・バヤット |
| 熟達への道のり |
鈴木ヘザー |
モクサアフリカ・レポート
2015年5月 |
マーリン・ヤング |
第30回
経絡治療学会記念学術大会 |
高嶋 正明 |
| 金沢信二郎氏を偲んで |
スティーブン・ブラウン |
|
2015年03月 No 63
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コウル |
| クリニックにおける伝統的本治法 |
グレッグ・ウィリアムズ |
| 作り話の鍼灸治療 |
岩下 秀明 |
| 灸点アップデート |
フェリップ・カウデット |
予備調査プロジェクト:
生体肝移植被験者における東洋医学的評価 |
ジェフリー・ダン |
| お灸 不確かな未来のフィールド医学となるか |
マーリン・ヤング |
| 医食同源 |
水谷 潤治 |
| 鍼灸と指圧で快適ライフ |
パメラ・エレン・ファガーソン |
| 生活習慣病と伝統医学 |
古江 崇 |
| メタボリック症候群の鍼灸治療 |
ファルク・サヒン |
| 長生き治療研究 |
メアリー S. ウォリス |
| 言霊ライフ治療師による手あてと鍼灸治療 |
トーマス・ダックワース |
| 指圧と鍼の融合 |
ミッチェル・ウォルフ |
| 積聚治療入門 Part1 |
高橋 大希 |
| 膝関節症 |
カール・ワグナー |
| 胆-心、心および胆の腹証の臨床研究 |
ファルク・サヒン |
| 五十肩を発症した糖尿病患者の症例 |
加賀 敏朗 |
| 七情が要因となって発病した症例 |
高嶋 正明 |
| レポート 積聚治療 ハワイセミナー |
矢田 真樹 |
| 2014年ハワイにおける積聚セミナー |
トム・ハール |
| セミナー・レポート Japan 5 In-Touch |
デイビッド・J・セト |
レポート
ジャパンセミナー5 |
トッド・ワイマー |
| レポート 東洋はりトレーニング |
ボブ・クイン |
書評 風に吹かれて
薬物耐性のある結核と貧困層 |
シェリル・コウル |
|
2014年11月 No 62
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
アンドリュー・フィッツチャールス |
| アンチエイジングと鍼灸医療 |
矢野 忠 |
| 古典にみる高齢者の鍼灸治療 |
松本 弘巳 |
| 老人病と鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
| 高齢者への私の鍼灸アプローチ |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
| 望診でわかる長寿の相 |
鈴木 万記子 |
| 操体先生、質問があります |
ランデー・ルーカス |
| 首藤流鍼灸術を用いた高齢者の治療 |
村田 守宏 |
| 高齢者における治療の症例 |
古江 崇 |
| 私のクリニック、その側面 |
カレブ・モルテンセン |
| 高齢者の治療について |
高嶋 正明 |
| 高齢者における変形性膝関節症と腹証 |
水谷 潤治 |
| 高齢患者のケーススタディー |
メアリー・ウォーリス |
| 高齢者の腹部に強い不快感を伴う便秘の治療 |
校條 由紀 |
| シニアとの共同作業のコツ |
パメラ・エレン・ファーガスン |
| 老いたる犬に新しい芸を教えることはできないまた他の慣用句 |
トム・インゲグノ |
| 高齢者の治療で思うこと |
笠 律子 |
| 私の治療室 |
徳山 文華 |
| 日本の高齢妊娠出産について思うこと |
高野 美加 |
| 高齢患者への鍼治療 |
ファルク・サヒン |
| 炎症への対症療法 |
トーマス・E・ダックワース |
様々な世代を治療する
南フロリダの治療院での移り変わり |
キャメロン・ビショップ |
| 治療の「用量」とゴルディロックスゾーン |
オラン・キヴィティ |
| コツコツ治療 |
大西 真由 |
| 妊娠初期における卵巣嚢腫の一症例 |
関 功芳 |
日本ニカラグア東洋医学大学の活動と
東洋医学高齢者治療の分析 |
八巻 晴夫 |
| パームスプリングスと鍼灸 |
児玉 亨 |
| モクサアフリカ 仮報告 |
マーリン・ヤング |
| モクサアフリカの出会い点と線 |
伊田屋 幸子 |
|
2014年07月 No 61
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
王居易教授による経絡触診と
早期鍼灸文献比較論 |
シェリー・オークス |
| 経絡診察 |
ジョナサン・チャン |
| 近代化社会と王居易氏による太陰経調整法(調整太陰經法) |
ジェフリー・ダン |
| 実際的灸療法 |
水谷 潤治 |
| 経絡システムの文化的物語 |
ニサ・タン |
アメリカの操体法
トップ会談 |
ランデー・ルーカス |
| 四海 第二部 |
クリス・マカリスター |
| 陰脈の臨床研究 任脈病症 |
ファルク・サヒン |
痛圧刺激によりステロイド離脱を試みた
膠原病11例の報告 |
長田 裕 |
| 黄班変性に対する鍼治療と直接 |
ランディ・クレア |
| 脈状と脳波 |
安士 正人 |
| アレルギーの一症例 |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| お灸の治療ノート |
高野 美加 |
| 灸治療 |
大西 真由 |
| 津液と気の統合 |
マーク・ペトルッジ |
| 首藤鍼灸院見学記 |
高嶋 正明 |
| 取穴法 熟練鍼灸師から学ぶ特攻穴 |
マーク・ペトルッジ |
| ネパール ヘルスキャンプに参加して |
芦井 新蔵 |
| モクサアフリカ日本講演 |
伊田屋ゆき |
| 2013年バルセロナ 灸法講習会 |
フィリップ・カウデット |
| 岩品安柳先生(Dr.Bear)とのクリニックでの一日 |
ボブ・クイン |
ドクター・ベアー(岩品安柳先生)による
鍼の基礎と経絡治療セミナー |
ダニエル・シルバー |
| NCNM 小児鍼クラブでのブレンダ・ロウ氏によるセミナー |
トッド・ワイマー |
| 東洋医学再考 |
高松 文三 |
精神的外傷とPTSD(外傷後ストレス障害)の治療
船水隆広先生によるセミナーの感想 |
ダニエル・シルバー |
ワークショップレポート
船水隆広先生サンタフェに行く |
ワイアット・クラジェスキ |
|
2014年03月 No 60
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 古典を臨床的に再現した伝統刺鍼術 |
スティーブン・バーチ |
第一回
国際王居易経絡理論シンポジウム |
ジェフリー・ダン |
先祖への敬意と我々のルーツの探求
経絡理論の創作と実用の源 |
王 居易 |
手の少陰心経と
手の厥陰心包経の症状の違いについて |
王 紅民 |
中国外の東洋医学の主客転倒の発展と
北京での現象 |
ジェイソン・ロバートソン |
| 腹鳴(グル音)の陰陽 |
ダニエル・シュールマン |
| 古典に言う経絡の真実を求めて |
品田 隆志 |
| 望診を生かす |
高嶋 正明 |
| 四海 |
クリス・マカリスター |
生命が終わり、また始まる
生命の循環と素問について想うこと |
ゼブ・ローゼンバーグ |
| 難経六十八難の選穴法とその臨床効果 |
ゾエ・ブレンーナー |
対談 パート 3
治療ポイントのとり方 |
形井 秀一 |
| 不妊症と妊婦に対する鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
| 頭位-骨盤位 治療の一症例 |
関 功芳 |
| 三陰交のお灸で逆子が治った |
亜記 |
温度にばらつきがあるのが
温熱用艾が点灸に適さない理由の一つ |
校條 由紀 |
| 慢性疾患を有するひとに対する鍼 |
ファルク・サヒン |
| 積聚治療によってパターンを変える |
ラー・アドコック |
| ティシャ・マロン先生による積聚治療 |
カレン・ビジャヌエバ |
鍼灸師 ティシャ・マロンへのインタビュー
積聚治療 |
ラー・アドコック |
特大の思いをアフリカに
ジェニー・クレイグとのインタビュー |
トン・バン・ハフェレン |
レポート:ニューメキシコ州サンタフェ市で開催された
水谷先生の灸講習会 |
カール・ワグナー |
|
2013年11月 No 59
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
シェリル・コール |
対談 パート 2
治療ポイントのとり方 |
形井 秀一 |
| 鍼灸の起源と思想について(3) |
松田 博公 |
| 触診と刺鍼時の施術者の自律反応 |
オラン・キヴィティ |
| 「座談会 治療ポイントのとり方」を読んで |
松本 弘巳 |
| 触診こそわが人生 |
水谷 潤治 |
| 日本式鍼灸の特徴 |
高嶋 正明 |
セラピストの手
触診の重要性について |
マータブ・バヤット |
| 偶然発見したツボ |
トム・インゲグノ |
| 繊細な触診に対する感想 |
ゾエ・ブレンーナー |
| 私の人生を変えた脈診 |
ボブ・クイン |
| 血圧に及ぼす指圧刺激の効果 |
日本指圧専門学校 |
| 指頭感覚を磨く |
笠 律子 |
| 恩書 |
高松 文三 |
| 鍼灸研究のジレンマ |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
古代治療の産物を再現して
『投与感覚とその反応』を使った治療の過程 (抄訳) |
ショーン・サットン |
| 月経異常に対する鍼灸治療 |
小窪 潤蔵 |
| 伝統鍼灸治療の証 |
古江 崇 |
| 陽脈-督脈の腹証の臨床研究 |
ファルク・サヒン |
伝統日本医学を取り入れた
伝統中医学教育の強化 |
エリザベス・タルコット |
| 整体灸 灸治療と骨格の改善 |
フィリップ・カウデット |
| イボのお灸治療 |
高野 美加 |
| お灸 Q and A |
大西真由
水谷 潤治 |
モクサフリカ アップデート
2013年5月 |
ジェニー・クレイグ
マーリン ・ヤング |
環太平洋経絡治療学会
創設者へのインタビュー |
エリザベス・タルコット |
ワークショップレポート
温竹灸 |
榎本 浩 |
|
2013年07月 No 58
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
スティーブン・ブラウン |
対談 パート 1
治療ポイントのとり方 |
形井 秀一 |
| 触診情報の重要性 |
小川 卓良 |
| 鍼灸の起源と思想について(2) |
松田 博公 |
| 鍼灸治療における瞬発的思考 |
高橋 英生 |
座右の書
『生きがいの探求』 |
関 功芳 |
| 私の世界を変えた本 |
アラン・ジャンソン |
書評
雑食動物のジレンマ―ある4つの食事の自然史 |
キャロル・ウエインガーテン |
座右の書
心の治癒力 |
高嶋 正明 |
| お灸ドクター 原志免太郎 |
大西 真由 |
| 一室の中での数百年に及ぶ教え |
キャメロン・ビショップ |
モクサフリカ アップデート
2013年5月 |
ジェニー・クレイグ
マーリン ・ヤング |
| 首藤流鍼灸術による臨床 |
村田 守宏 |
| 帯脈‐陽維脈における腹証の臨床研究 |
ファルク・サヒン |
| コミュニティー鍼灸モデルにおける経絡治療 |
ロバート・ハイデン |
| 足の湿疹への知熱灸治療 |
校條 由紀 |
| 実際的灸療法(35) 鍼灸真髄ーその4 |
水谷 潤治 |
| 脈診に表れた東日本大震災の予兆 |
鈴木 万記子 |
| Koshiバランスセミナー |
ボブ・クイン |
セミナーレポート
高橋 英生先生の
The Essential Spirit of Japanese Acupuncture |
マイケル・タリシュ |
セミナーレポート
心にゆだねるハワイ島 |
トッド・ツレッツキー |
| 船水隆広氏によるハワイセミナーのリポート |
ボブ・クイン |
|
2013年03月 No 57
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
パート 2
虚実補瀉 |
ステーブン・バーチ |
| 浅い鍼が起す「気至る」と奇跡的治癒 |
鈴木 万記子 |
Short Q and A
古い艾でうまく捻る方法は? |
|
| 鍼灸の起源と思想について |
松田 博公 |
| 背診の理論と応用 |
小窪 潤蔵 |
妊娠時の吐き気と嘔吐に対する
兪府への皮内針の効果 |
コリーン・スミス |
| 論考 |
トーマス·ダックワース |
| 耳鳴りの鍼灸治療 |
校條 由紀 |
温竹による経絡周波数の灸
パート2 |
オラン・キヴィティー |
| カッピングの臨床応用 パート2 |
バート・ウォルトン |
| カッピングの臨床応用 |
バート・ウォルトン |
| 鍼灸による難病治療の課題 |
マータブ・バヤット |
| 病巣の重要性 |
ファルク・サヒン |
| 鍼灸の知恵の探究 |
徳山 文華 |
| 自宅灸の利点 |
大原 ゆり |
| 慢性疾患への挑戦 私の住む島について |
高嶋 正明 |
| 手の疾患の灸治療 |
水谷 潤治 |
| 書評 松島に昇る月 |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
モクサフリカ アップデート
結核の研究がついに始まる |
マーリン・ヤング
ジェニー・クレイグ |
セミナーレポート
松本岐子 日本留学セミナー2012 |
グレース・ロリンズ |
| ヒマラヤの麓でボランティア |
西山 昭弘 |
| セミナーレポート水谷 潤治 – 竹筒灸ワークショップ |
シェリル・コール
カット・アオ |
|
2012年11月 No 56
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
今と昔における臨床の考
補瀉と虚実、異なる考え方 |
ステーブン・バーチ |
日本鍼灸を思う
Part2 ハワイセミナー |
小林 詔司 |
最初はまごつき、
やってみたら結果がいいという話 |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
| 気で誰かをサンドイッチする? |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 背診の理論と応用 |
小窪 潤蔵 |
鍼作法の新解析
Part2 |
石田 安男 |
| 易の思考方法(2) |
藤原 典往 |
| 無の枢軸 鍼治療における時代の流れ |
チャールズ・チェイス |
| 編集者への手紙 |
メアリー・S・ウォリス |
| 生涯傷もの |
フィリップ・C. J.ストロング |
| カッピングの臨床応用 |
バート・ウォルトン |
| クリニックの多様性 |
キム・ロサド |
| 白鶴太極療法 |
カール・ワグナー |
| 幻肢痛 |
マータブ・バヤット |
| Q and A 中央励兌について |
バート・ウォルトン |
| 歯周病ケアと黄蓮解毒湯 |
安士 正人 |
| 現代の師弟関係 |
アラン・ジャンソン |
| 歯痛の特効穴 柳谷一本バリ |
金澤 信二郎 |
モクサフリカ アップデート
結核の研究がついに始まる |
マーリン・ヤング
ジェニー・クレイグ |
履物は入り口で脱いで
垣間見た日本の診療所における不妊治療 |
キャメロン・ビショップ |
| 第五十四回経絡治療夏期大学の報告 |
古江 崇 |
| 2012年東京国際鍼灸 セミナーリポート |
ジェフリー・ダン |
| 谷岡小児鍼セミナー |
グレッチェン・ロレンソン |
| 名人セミナー |
高松 文三 |
|
2012年07月 No 55
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
スティーブン・ブラウン |
| 日本鍼灸を思う |
小林 詔司 |
皮膚移植が必要といわれた
皮膚炎が知熱灸で改善した1例 |
校條 由紀 |
| つわりの治療 |
村田 守宏 |
肝、肝小腸、小腸の
腹証の臨床研究 |
ファルック・サヒン |
| 積聚治療の症例 |
シンシア・クワトロ |
中米ニカラグア共和国における
東洋医学25年の歩み Part2 |
八巻 晴夫 |
| 独創的人間医学 |
アンディー・カロゾス |
| 『箱灸』について |
関 功芳 |
| クルーズ船で働く |
戸田 さやか |
| 死体に対し鍼を施す意味とは何か? |
ジェフリー・ダン |
| 気の声を聴く |
ポーラ・スティール |
| 足心 |
松本 岐子
モニカ・コベイレッカ |
| 言霊いのち経絡治療方法とプロトコル |
トーマス・E・ ダックワース |
| 「一リットルの涙」と「茶碗一杯の青汁」 |
高松 文三 |
| 特異な臨床経験 |
アラン・ジャンソン |
| 鍼作法の新解析 |
石田 安男 |
| 伝統治療と独創性 |
古江 崇 |
特効治療の手法
―幻痛― |
パメラ・エレン・ファーガソン |
はちょうの灸
Part2 |
坂本 浩一 |
| 灸頭皮内鍼と温灸皮内鍼テクニックpart4 |
アーロン・ルービンシュタイン |
ドイツにおける
Ohashiatsu:35年 |
大橋 渉 |
| 現在の艾製造について |
前川 高志 |
モクサフリカ・アップデート
2012年5月 |
ジェニー・クレイグ |
レポート
第11回伝統鍼灸セミナーの報告 |
長戸のり子 |
レポート
積聚セミナー:ハワイ州コナ市 |
アーランド・トゥルイット |
| M-Test 初級セミナー |
ジェイソン・ベイト |
|
2012年03月 No 54
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
ジェフリー・ダン |
| 虚実と補瀉 |
池田 政一 |
| 虚実問答 |
水谷 潤治 |
| 虚実補瀉について考える |
ジェフリー・ダン |
| 虚実、補瀉 |
トーマス・E・ダックワース |
| 補法のお灸、瀉法のお灸 |
校條 由紀 |
| 学びの逸話 |
ボブ・クイン |
長野式の気水穴処置法
(金水穴処置法) |
グレース・ロリンズ |
心に残る症例から
打鍼と鍼道発秘の応用 |
川瀬 邦裕 |
| 衝脉、陰維脉の病理の臨床研究 |
ファルック・サヒン |
| 私が禅指圧セラピストになった理由 |
ジュリー・ブリジット・ムーア |
| 易の思考方法(その1) |
藤原 典往 |
| シーボルトと石塚宗哲Part 2 |
マティアス・ヴィグル |
モクサフリカ・アップデート
2011年12月 |
ジェニー・クレイグ
マーリン・ ヤング |
| ドクターINEON MOONとの実習体験 |
ジェイク・P・フラトキン |
中米ニカラグア共和国における
東洋医学25年の歩み Part1 |
八巻 晴夫 |
| レポート 「己れを尽くす」鍼灸師を育てる |
高橋 英生 |
| 熱の小道具 ドイツでの灸 |
トン・バン・フフェレン |
| セミナーリポート MTest上級 |
伊田屋 ゆき |
| 第2回積聚治療セミナー 小林詔司先生 |
パメラ・ソカッチ |
| 第三東京セミナーの思い出 |
スティーブン・ブラウン |
| 温かい手と暖かい心 |
ジョン・トンプソン |
レポート
第3回東京セミナーと第53回経絡治療夏期大学 |
スティーブン・シロキー |
私の日本での体験談
2011年「東京3」セミナー |
ジェニカ・ウィルダウ |
|
2011年11月 No 53
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 鍼灸における瞑眩について part3 |
横田 観風 |
灸頭皮内鍼と温灸皮内鍼テクニックpart3
手と足の治療 |
アーロン・ルービンシュタイン |
| 放射線被曝を生き延びる |
久保田 直紀
EJ ポター・久保田 |
一過性大腿骨頸部
骨粗鬆症に関する症例 |
ピーター・イエーツ |
ケースレポート
変形性膝関節症 |
大原 ゆり |
モクサフリカ・アップデート
2011年8月 |
ジェニー・クレイグ
マーリン・ ヤング |
人間の表と裏
ホモ・セクシュアル診療例 |
ディタ・サローバ |
| 『はちょう』の灸 |
坂本 浩一 |
| 竹筒灸 |
水谷 潤治 |
一番切れるナイフではないけれども
学びに関しての考察 |
エドワード・オベイデイ |
弟子から旅人そしてさらなる未来へ
現代の生徒の伝統の道 |
トーマス・ダックワース |
| オーストラリアの見習い制度 |
アダム・マッキントッシュ |
| 従弟制度は大いに有効である |
キミコ・ナイト |
| 徒弟制度的修行についての考察 |
ナイジェル・ドーズ |
| 消えゆく徒弟制度の芸術 |
キム・ロサード |
| 弟子に関して |
ジェイソン・ハックラー |
| 鍼灸術の芸術性 |
カレブ・モーテンセン |
| 二人の師と出会って |
金森 亜記 |
書評 スティーブン・バーチ著
『小児鍼:小児のための日本鍼』本とDVD |
ブレンダ・ロウ |
Traditional Japanese In-Touch Acupunctureと
第53回鍼灸経絡治療夏期大学に参加して |
古江 崇
キース・ヒューズ |
曾栄修先生
第三回傷寒論会議を振り返って
2011/4/29 ~ 5/1 |
ゼブ・ ローゼンバーグ |
レポート
積聚治療アメリカセミナー |
矢田 真樹 |
| 積聚治療セミナーについて |
川並 弘樹 |
| ネパールにおける鍼灸ボランティア |
熊木 亜夫 |
|
2011年07月 No 52
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
ジェフリー・ダン |
| 艾はどのように効果を出すか? part2 |
ジェニー・クレイグ
マーリン・ヤング |
| 鍼灸における瞑眩について part2 |
横田 観風 |
| 経絡の特性について part2 |
王 居易 |
| 新たな地平へ |
斉藤 哲朗
シェリル・コール |
気と語る技を学ぶ
深層指圧における診断および治療法 |
ピーター・スクリヴァニック |
| カナダ・ブリティッシュコロンビアにおける指圧治療 |
テッド・トーマス |
オンタリオ州
指圧コミュニティが直面している問題 |
ピーター・スクリヴァニック |
| 地震!地震! |
エドワード・オベイデイ |
| 痛圧刺激による膝関節痛の治療 |
長田 裕 |
シーボルトと石塚宗哲
江戸時代の国を超えた鍼灸師弟 |
マティアス・ヴィグル |
| 灸頭皮内鍼と温灸皮内鍼テクニックpart2 |
アーロン・ルービンシュタイン |
| 東洋医学に導かれて |
フランク・太田 |
| ジェフリー先生からの問いかけに対する答え |
池田 政一 |
| 徒弟制度は必要 |
椿山 清秀 |
| 弟子の詩 |
トーマス・ダックワース |
| 新米から師匠への道 |
ピーター・イエーツ |
| 現代の師弟関係 |
カレブ・モーテンセン |
指導
助手と共に働くことについて |
パメラ・エレン・ファーガソン
デブラ・ダンカン・パーシンガー |
| 私の徒弟期間 伝統に従って |
スーザン・デンボ |
| 私の「師弟関係」 |
森 孝史 |
| 翁先生の思い出 |
反町 大一 |
北米における
鍼灸学校卒業生向け継続学習のあり方 |
ボブ・クインクイン |
| 師匠と弟子 |
村田 守宏 |
| 正体鍼法の研修制度 |
マイケル・ダブロスキー |
| 「徒弟」 |
トレイシー・コンラッド |
| 師弟制度 |
カール・ワグナー |
| 現代の内弟子 |
モニカ・コビレカ |
| お灸2日間集中講座に参加して |
本多 進 |
| ピーター・イエーツ氏によるセミナー記 |
トム・インゲグノ |
モクサフリカ・アップデート
2011年5月 |
ジェニー・クレイグ |
|
2011年03月 No 51
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
ジェフリー・ダン |
| 艾はどのように効果を出すか? part1 |
ジェニー・クレイグ
マーリン・ヤング |
| 鍼灸における瞑眩について part1 |
横田 観風 |
| 経絡の特性について part1 |
王 居易 |
| 本治法と標治法 |
大上 勝行 |
| 吉益東洞医術の源始 |
ジューン・ヒー・リー |
| 突発性難聴の一症例 |
関 功芳 |
書評
日本鍼灸101:初心者のためのガイドライン |
アンドリュウ・フィッツ チャールス |
| 山元敏勝先生と山元新頭皮鍼(YNSA) |
ダイアン・ユリアーノ |
Y.N.S.A 頭鍼療法の脳神経穴
(東西医学の狭間で) |
ファルク・サヒン |
書評
山元式新頭鍼療法 |
ボブ・クイン |
脳震盪後の頭痛と頭部の血
松本岐子式鍼灸を用いたケーススタディ |
グレース・ローリンズ |
| 初心者のための灸の方程式 |
アダム・マッキントッシュ |
| 知熱灸で改善した口内炎(アフタ)の1例 |
校條 由紀 |
| ライム病と灸療 |
大西 真由
水谷 潤治 |
| 読者から編集者へ |
ラリー・ウェルシュ |
| 日本人の健康と長寿の秘密 |
久保田 直紀
ユウジニア 久保田 |
| 中黄膏(ベルクミン)とアレルギー性鼻炎 |
安士 正人 |
モクサフリカ最新情報
2011年1月 |
ジェニー・クレイグ |
レポートヘルスキャンプ 2010
鍼灸ボランティア治療 in ネパール・ビルガンジー |
山川 義人 |
レポートー2010年
Mテストセミナー |
ケン・グロウアッキ |
最小限で最大限の効果を
ブレンダ・ロウの氏による小児鍼セミナー |
トレイシー・ソーン |
|
2010年11月 No 50
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 50号発行へのお祝いの言葉 |
スティーヴン・バーチ
スティーブン・ブラウン
ジェ フリー・ダン
アンドリュー・フィッツチャールス
池田 政一
神谷 一信
松本 弘巳
首藤 傳明 |
| 痛圧刺激による梨状筋症候群の治療 |
長田 裕 |
| 経絡とは、ツボとは何か? |
バート・ウォルトン |
| 灸頭皮内鍼と温灸皮内鍼テクニックpart1 |
アーロン・ルービンシュタイン |
| 再びお血について |
池田 政一 |
| 扁桃炎による高熱頻発 |
谷岡 賢徳 |
| 気は血をめぐらせる 確証編 |
カレブ・モーテンセン |
経筋:
エネルギーが筋膜と合流するところ Part2 |
デボラ・バレンタイン・スミス |
| 症例報告「うつ症状」 |
加藤 浩仁 |
| 積聚治療への移行 |
ランディ・ルーカス |
| 経穴、太谿(KI-3)に関する疑問 |
ニーベン・オーヘル |
Moxafricaレポート
カンパラへの旅 |
マーリン・ヤング |
難経と関連する古典群
英語翻訳についての調査 |
ゼビ・ローゼンバーグ |
臨床に活かす気の流し方
人を救い自分も救われるために Part2 |
岩下 秀明 |
鍼灸と禅-鍼は人なり-
治療における存在の役割を求めて-Part2 |
トッド・トレッツキー |
| ワトソンの水槌脈 |
グレゴリー・チェルニッシュ |
実際的灸療法(34)
沢田流聞書「鍼灸真髄」Part3 |
水谷 潤治 |
2010年5月9日・10日、スイス・バーゼル市で行われた
水谷 潤治先生による「灸治療講座」について |
アレクサンダ ー・シューマン |
2010年7月24~26日開催
レポート 水谷 潤治先生セミナー |
古江 崇 |
福島先生のボストンお灸ワークショップと
ニカラグア鍼灸学校訪問 |
倉澤 由美 |
| 第52回経絡治療学会主催夏期大学に参加して |
古江 崇 |
| レポート鍼灸経絡治療夏期大学 |
笠 律子 |
|
2010年07月 No 49
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 東と西の医のアート |
日野原 重明 |
江戸時代の鍼灸教育
日本式カリキュラム対中国式カリキュラム |
マティアス・ヴィグル |
前号NAJOMの記事に鼓舞されて
瘀血についての考察 |
ナイジェル・ドーズ
コリーン・コーラー |
| 後藤艮山の「一気留滞論」と「五極の灸」 |
福島 哲也 |
| ストレスによる円形脱毛への鍼灸治療 |
校條 由紀 |
経筋:
エネルギーが筋膜と合流するところ |
デボラ・バレンタイン・スミス |
| 指圧治療の利点 |
バート・ウォルトン |
サーキット・ニードリング
古典中国鍼灸と体内経絡・臓器異常への回路鍼 |
マーク・シーム |
| カンパラ − 2010年3月 |
マーリン・ヤング
ジェニー・クレイグ |
2009年12月
M-Test:向野先生を訪ねて |
伊田屋 ゆき |
| 平凡 |
高松 文三 |
| Letter to Editor |
パメラ・ファーガソン |
| 超診断 |
パメラ・ファーガソン |
鍼灸と禅-鍼は人なり-
治療における存在の役割を求めて-Part 1 |
トッド・トレッツキー |
他には何も
東洋はりの治療における意の役割について |
トン・バン・ホッフレン |
臨床に活かす気の流し方
人を救い自分も救われるために |
岩下 秀明 |
自分自身の経験から感じたこと
随筆『気の病』 |
笠 律子 |
| お灸の魅力 Part2 |
大原 ゆり |
書評
ブルース・ロビンソン医学博士の著作 |
ジェフリー・ダン |
経絡治療の探求
本治法と標治法のバランス
スティーブン・ブラウンサンタフェセミナー
(2010年4月17日、18日) |
カール・ワーグナー |
ジェフリーダン氏による「腰調整治療」
オレゴン州ポートランド(2010年3月6、7日) |
ボブ・クイン
トレイシー・ソーン |
|
2010年03月 No 48
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 鍼灸医学から見た瘀血 |
間中 喜雄 |
| 瘀血について |
岡田 明祐 |
知熱灸治療で改善した
於血によるにきび症の1例 |
校條 由紀 |
| 瘀血についての管見 |
大塚 敬節 |
| 瘀血証について |
久住 恒夫 |
| 瘀血の治療 |
池田 政一 |
| 見える瘀血、見えない瘀血 |
児玉 亨 |
日本鍼灸を求めて
第1回 傳田光洋 part3 |
松田 博公 |
| 積聚治療による腰痛治療 |
原 オサム |
| 超旋刺の症例 |
村田 守宏 |
「この小さな子豚は…」
奔豚症の近世、現代的解釈と治療 |
ナイジェル・ドーズ |
| 熱くない無痕透熱灸への誘い |
平戸 幹四郎 |
| ぎっくり腰治療 |
木下 信幸 |
レポート 2009年9月20、21日 東京
いやしの道協会合宿 |
高橋 英生 |
気の世界
2009年日本旅行 |
アーランド・ツルーイット |
レポート
ボストンお灸セミナー |
杉山 正彦 |
『経絡治療の探求』
スティーブン・ブラウン氏と共に |
マーク ・ペットルッジ |
レポート
2009年ボストン上級積聚セミナー |
ケン・グロウアキ |
レポート
小林詔司先生の積聚セミナー |
シンシア・クアトロ |
2009年11月開催
S・ブラウンのブリスベンセミナーに参加して |
古江 崇 |
|
2009年11月 No 47
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
ジェフリー・ダン |
東洋医学の原点「気」へのアプローチ
皮膚が色や音を識別する!? |
間中 喜雄 |
| 間中喜雄と間中病院 |
松岡 賢也 |
| 日中両国に於ける鍼灸の異同 |
間中 喜雄 |
伝統的東アジア医学(TEAM)分野における
間中博士の洞察と貢献 |
スティーブン・バーチ |
吉元昭治医師に聞く
奇人・変人を歓迎した間中精神 |
松田 博公 |
| 証について |
間中 喜雄 |
アブストラクト:間中喜雄著
鍼灸医学から見た血 |
スティーブン・ブラウン |
| 二人の大先生との出会い |
スティーブン・ブラウン |
観察学的研究
間中博士の肝機能値異常に対する鍼灸療法 |
アミチ・サラー・フィシュバック |
河童随筆
大量療法と微量療法 |
間中 喜雄 |
| システム学的に見た経絡概念 |
間中 喜雄 |
| 非常に難解な症状の成功例 |
スティーブン・バーチ |
| 鍼灸による癒着の治療 |
マーク・ウェブスター |
| イオンコードと10年 |
ボブ・クイン |
| 間中先生と私と三人の女性 |
水谷 潤治 |
| 書評:間中博士の本 |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
| 2009年バルセロナICEセミナーの報告 |
マヌエル・ロドリゲス |
|
2009年07月 No 46
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
アンドリュー・フィッツチャールス |
| ツボ探しの手 part2 |
戸ヶ崎 正男 |
日本鍼灸を求めて
第1回 傳田光洋 part2 |
松田 博公 |
| 深谷灸法の多壮灸 |
新間 英雄 |
| 巨刺を用いた症例 |
関 功芳 |
| 松田博公とTOKYO夏期セミナー参加者の座談会 |
スティーブン・ブラウン
ジェフリー・ダン
その他 |
| 治療余話 |
神谷 一信 |
| 「補完医療」法案の可否ースイス |
アレクサンダー・シューマン |
| 鍼灸、社会適応と平等性 |
ジュリアナ・クンボ |
漢方- 古代医術 現代医学 (9)
過敏性大腸症候群 (IBS) の漢方治療-第3回 |
ナイジェル・ドーズ
マリ・マックレーン |
| 東洋はり医学における舌診の利用 |
スーザン・ファイファー |
| 犬の灸治療 |
根湖田エリ子 |
知熱灸で
ネックレスによる肌荒れが改善した1例 |
校條 由紀 |
| 手技 |
大原 ゆり |
| 良くなってくれない患者について思うこと |
カール・ワグナー |
| 水谷潤治ポートランドお灸セミナー 2009.4.25-26 |
ボブ・クイン |
| 陰陽考 |
ボブ・クイン |
| ネパールの棒灸 |
畑 美奈栄 |
実際的灸療法(33)
鍼灸真髄Part2 |
水谷 潤治 |
池田政一 第9回サンフランシスコセミナーの報告
『傷寒論と鍼灸』 |
長戸 のり子 |
首藤傳明 サンフランシスコセミナー 2009.5.2-3
『忘己利他』 |
アンドリュー・カロゾス |
首藤傳明 サンフランシスコセミナー 2009.5.2-3
『鍼は人なり』 |
キャメロン・ビショップ |
|
2009年03月 No 45
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
スティーブン・ブラウン |
| 治療部位としての頭部の可能性 part2 |
鈴木 育雄
梶間 育郎
蔡 暁明
井上 悦子 |
日本鍼灸を求めて
第1回 傳田光洋 part1 |
松田 博公 |
| 日本の美容鍼灸 |
北川 毅 |
古松奨励流エネルギー医学
松竹梅紋に関するアートの概観 Part2 |
デービッド・ロプリオレ |
実際的灸療法(32)
鍼灸真髄-Part1 |
水谷 潤治 |
| 症例:フルンケル(癤、癰)を中医で治療する |
マーク・ウエブスター |
| 鍼灸、社会適応と平等性 |
ジュリアナ・クンボ |
地理が異なることによるツボ位置の変化
2箇所のクリニックでの観察 |
トム・インゲグノ |
| マクロビオティック |
高松 文三 |
伝統中医医学から東洋はりへ
ある男の旅 |
ミッチェル・ウルフ |
臨床講演
異なる個々人(患者)にとっての良い脉状とは |
中田 光亮 |
積聚療法セミナーPart2
症例報告 |
ロバート・グレーシー |
| 日本体験記 東京セミナー2008 |
レジナルド・フィルホ |
| 2008年 東京セミナー後の体験記 |
マリオラ・ストラーバーグ |
| サンディエゴ Mテスト講習会 |
金澤 信二郎 |
| 十月・霧の三日間 |
アナンダ・デヴィ |
AOBTA集会
(サンディエゴ、2009年1月8日~12日) |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 腰のバランスの取り方 |
アンドリュー・フィッツチャールズ |
|
2008年11月 No 45
|
詳細
|
なし |
| Editorial |
水谷 潤治 |
| 治療部位としての頭部の可能性 part1 |
鈴木 育雄
梶間 育郎
蔡 暁明
井上 悦子 |
| 日本鍼灸の遺産を求めて |
マティウス・ビッゴロス |
対談:あらゆる病は「冷え」から起こる
「冷え」は東西両医学の架け橋となるか |
川島 朗
原 オサム |
| 頚部神経根症の治療(続編) |
長田 裕 |
| お灸の魅力 |
大原ゆり |
| ツボ探しの手 part1 |
|
| 経絡触診 |
王 居易
ジェーソン・ロバートソン |
| Book Review |
ジェフリー・ダン |
| 現代社会おける鍼灸需要と変化の可能性 |
北川 毅 |
| 触診と特殊技術についての質疑応答 |
パメラ・エレン・ファーガソン |
| 書評 |
スティーブン・ブラウン |
| 石坂宗哲:誤解された天才 |
久保田 直紀 |
| 堅実な基礎作りをするために |
エブリー・ヤッケル |
妊娠中の皮膚疹が
局所知熱灸で消失した症例 |
校條 由紀 |
福島哲也先生による
深谷式お灸ワークショップ |
カン・チャン |
| 恒例 積聚治療セミナー |
シンシア・クワトロ |
| 傷寒論づくし、夏の祭典! |
ナイジェル・ドーズ |
2008年の東京セミナー
日本鍼灸の心への旅 |
ジョン・トンプソン |
|
2008年07月 No 44
|
詳細
|
なし |
経絡テスト(Mテスト)
からだの動きで診るツボ療法 |
向野 義人 |
| 頚部神経症の治療 part2 |
長田 弘 |
漢方-古代医術 現代医学(8)
過敏症大腸症候群(IBS)の漢方治療 |
ナイシェル・ドウズ
マリ・マックレーン |
| 腹診の要領 |
松本 弘己 |
| 超浅刺の症例 |
村田 守宏 |
| 日本の鍼灸について |
形井 秀一 |
| 担癌患者の一症例 |
関 功芳 |
| 深谷灸法について |
福島 哲也 |
積聚治療による
月経随伴性気胸の治療
症例報告 |
加藤 浩仁 |
| 後陽陵泉と多発性硬化症の不思議な実例 |
カール・ワグナー |
| 道具から考える打鍼法 |
高橋 英生 |
古松奨励流エネルギー医学
松竹梅紋に関するアートの概観 Part1 |
デービッド・ロプリオレ |
| ローリング・エクササイズ |
本田 明 |
| 活法-人を生かす |
トーマス・E・ダックワース |
| 形井秀一先生のセミナーレポート |
デール・ホワイト |
| 東洋はりセミナーレポート |
バイロン・バース |
| 水谷潤治先生によるお灸の集中講座 |
トレシー・ソーン |